
ご家族が亡くなられ、残された財産が一体どれくらいあるのか、正確に把握できず困ってしまうケースは珍しくありません。
相続手続きを進めるうえで、預貯金や不動産、株式など、多岐にわたる財産をどのようにリストアップし、評価すればよいのかわからず、途方に暮れている方も少なくないでしょう。
そのため、相続財産目録の作成は、相続手続きの最初のステップであると共に重要な作業です。しかし、財産の種類が多かったり、どこから手をつけてよいか分からなかったりすると、正確な目録を作成できません。
遺産分割協議をスムーズに進めるには、目録の正確な作成が必須です。
この記事では、相続財産目録とは何か、作成の流れやポイント、記載例について詳しく解説します。
相続財産目録とは?
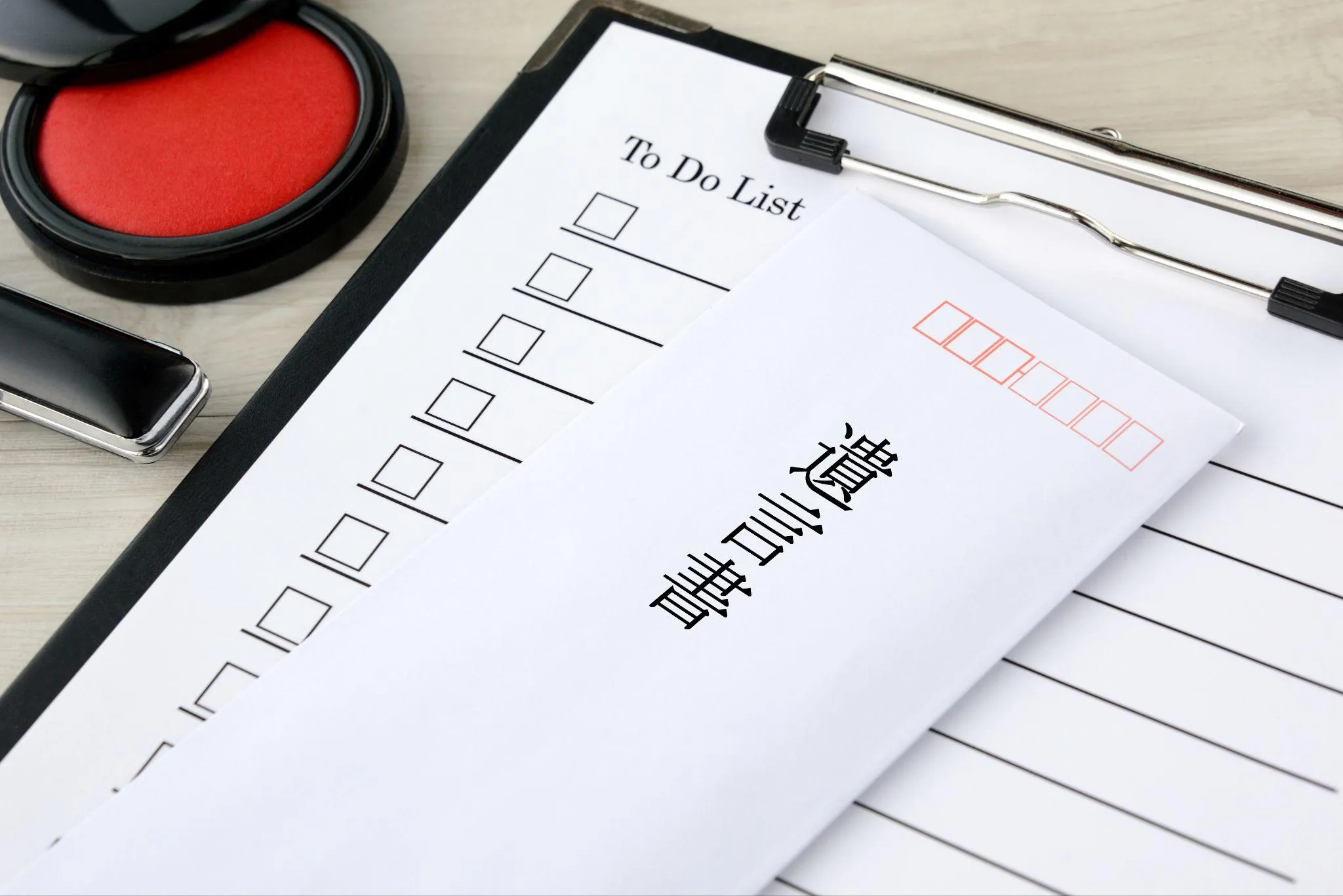
相続財産目録とは、被相続人が亡くなった際に残したすべての財産を一覧にまとめた書類です。
預貯金や不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産もすべて含めて記載します。
相続財産目録を作成することは、相続人全員が故人の財産の全体像を正確に把握するために欠かせません。
遺産分割協議を進めるうえでの基礎資料となるだけでなく、相続税の申告や相続放棄・限定承認の手続きを行う際にも必要になります。
相続財産目録を作成する流れ
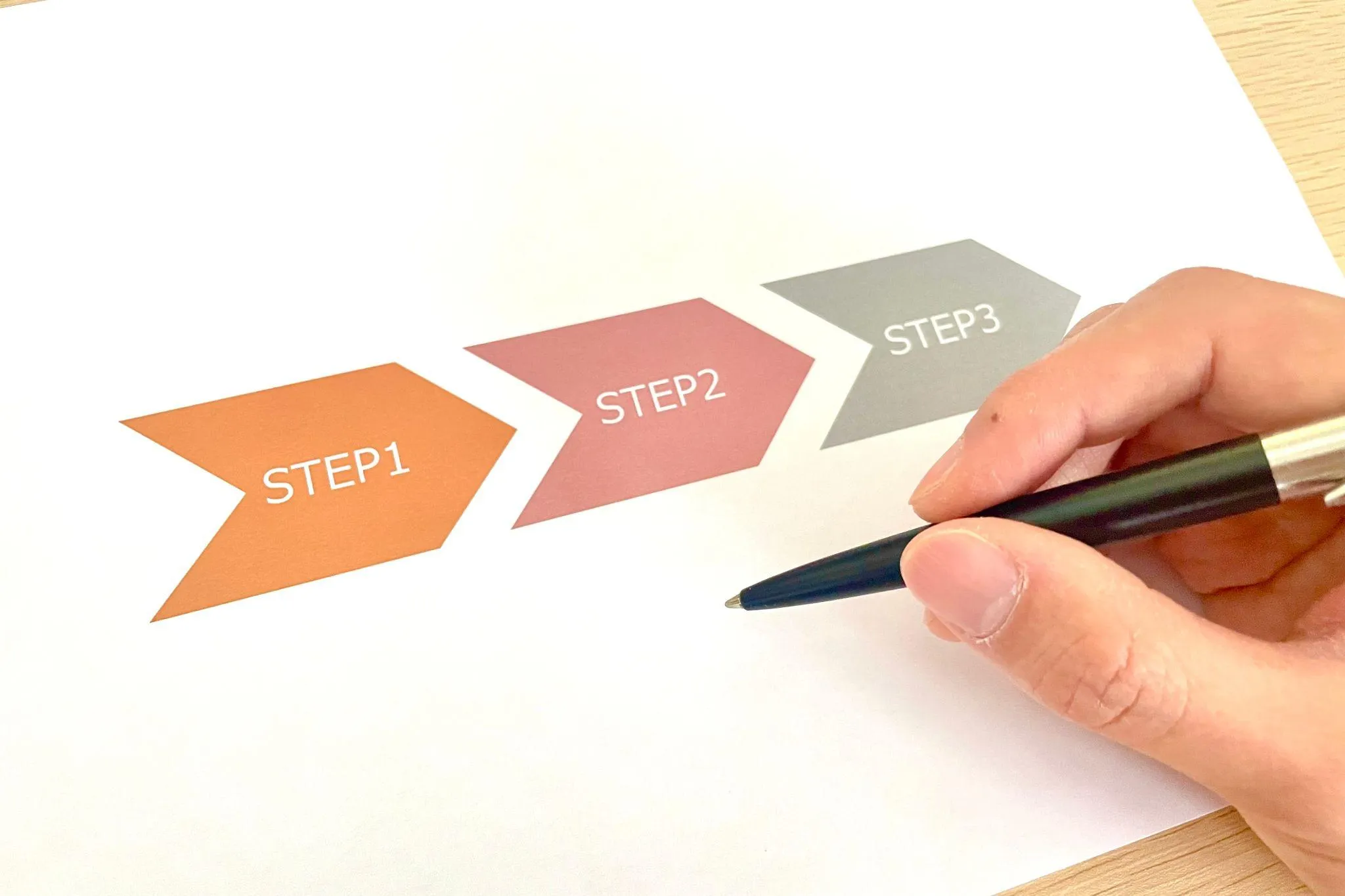
相続財産目録の作成は、相続手続きのなかでも基礎となるステップです。
正確な相続財産目録を作成するには、段階を踏んで慎重に進める必要があります。
- 相続財産の調査
- 財産特定のための資料を収集
- 相続財産目録の作成
まずは故人の財産を隈なく調査し、内容を正確に把握することからスタートします。その後、それぞれの財産を特定するための具体的な資料を集め、最終的にそれらを整理して相続財産目録を作成する流れが基本です。
ここでは、相続財産目録を作成する流れを詳しく解説します。
相続財産の調査
相続財産目録を作成する際は、まず被相続人が所有していたすべての財産を徹底的に調査しましょう。
この段階で洗い出しが必要なプラスの財産は、多岐にわたります。
- ・預貯金
- ・不動産
- ・有価証券
- ・自動車
- ・宝飾品
- ・美術品
- ・骨董品
また、マイナスの財産も、漏れなく洗い出す必要があります。
- ・借金
- ・ローン
- ・未払金
- ・連帯保証債務
故人の自宅を丹念に探し、郵便物や通帳、証券、契約書などを確認すると、財産の全体像を把握する手がかりを得られるでしょう。
財産特定のための資料を収集
相続財産の調査で洗い出した項目は、それらの財産を特定し、評価するための具体的な資料を収集しなければいけません。
例えば、預貯金なら金融機関からの残高証明書、不動産なら固定資産評価証明書や登記事項証明書、有価証券なら証券会社からの残高証明書や取引報告書などが必要です。
借金やローンについては、借入先の金融機関からの残高証明書などを取得しましょう。
これらの資料は、相続財産目録に記載する具体的な内容や評価額の根拠となるため、正確に集める必要があります。
相続財産目録の作成
必要な資料が揃ったら、相続財産目録の作成に入ります。
書式は特に定められていませんが、一般的にはプラスの財産とマイナスの財産を明確に区別し、それぞれに具体的な内容や数量、評価額などを記載します。
不動産や有価証券などの評価が難しい財産は、専門家の意見を聞きながら適切な評価額を記載するべきです。
作成した目録は遺産分割協議や相続税申告など、その後の相続手続きのさまざまな場面で活用される重要な書類となるでしょう。
相続財産目録の記載内容とポイント

相続財産目録は財産をリストアップするだけでなく、内容を具体的かつ正確に記載しなければいけません。
特に、プラスの財産とマイナスの財産を明確に区別し、それぞれの財産の種類に応じた評価額を算出する点は重要です。
ここでは、相続財産目録の記載内容とポイントをそれぞれ詳しく解説します。
記載すべき主な項目
相続財産目録には、さまざまな項目の記載が必要です。
まず、作成年月日と作成者の氏名を明確に記載しましょう。次に、故人の氏名や住所、生年月日、死亡年月日を正確に記入します。
肝心な財産については、以下のプラスの財産を具体的に列挙します。
- ・預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、残高)
- ・不動産(所在地、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、固定資産評価額)
- ・有価証券(証券会社名、銘柄、口数、評価額)
- ・自動車(車種、登録番号、評価額)、動産(骨董品、美術品など)
さらに、借金(借入先、残高)や未払金(種類、金額)などのマイナスの財産も漏れなく記載しなければいけません。
プラスとマイナスの財産を区別する
相続財産目録を作成する際のポイントは、プラスの財産とマイナスの財産を明確に区別して記載することです。
これにより、被相続人の財産の全体像を正確に把握できます。
例えば、プラスの財産は現金・預貯金、不動産、有価証券といったカテゴリに分けて記載し、それぞれに金額や評価額を記入しましょう。一方、マイナスの財産は借金、未払金などのカテゴリに分け、負債の内容と金額を具体的に記載します。
それぞれの区別は、相続税の計算や相続放棄・限定承認を検討する際に欠かせません。
不動産は評価額を算出する
相続財産目録に不動産を記載する際は、評価額を正確に算出する必要があります。
不動産の評価額には、固定資産税評価額や相続税評価額、時価などがありますが、一般的には固定資産税評価額を記載する場合が多いです。
固定資産評価証明書は、毎年送付される固定資産税納税通知書に同封されているか、市区町村役場で取得できます。
また、評価方法はいくつかあるため、どの評価額を記載するかは、目録の利用目的(遺産分割協議、相続税申告など)によって判断し、必要であれば専門家に相談して算出しましょう。
パソコンで作成する場合はすべてのページに署名捺印が必要
相続財産目録をパソコンで作成する場合は、すべてのページに相続人全員が署名捺印しなければいけません。
相続財産目録が複数のページにわたる場合、各ページに署名と捺印がないと、後からページが差し替えられたり、内容が改ざんされたりするリスクがあります。これにより、目録全体の信頼性が損なわれる可能性があるため、署名捺印は慎重に行ってください。
すべてのページに署名と捺印をすれば、目録の内容が確定され、相続人全員が内容に同意していることを明確に示せます。
相続財産目録の記載例

相続財産目録は、具体的にどのような形式で記載すればよいのかを理解すれば、実際に作成する際の参考になります。
記載すべき情報や表現方法は、財産の種類ごとに異なるため、いくつかの記載例を把握しておくべきです。
ここでは、相続財産目録の記載例を紹介します。
預貯金や現金の記載例
預貯金や現金を相続財産目録に記載する際は、金融機関名や支店名、預金種別、口座番号、被相続人の死亡時点での残高を明確に記載します。
記載例は、以下の通りです。
- ・普通預金: 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567 〇〇円
- ・定期預金: 〇〇信用金庫 〇〇支店 定期預金 口座番号 8901234 〇〇円
- ・現金: 自宅保管 〇〇円
現預金は流動性の高い財産であり、遺産分割協議でも欠かせない要素です。そのため、正確な残高の記載が必要になります。
有価証券の記載例
有価証券を相続財産目録に記載する際には、証券会社名や銘柄、口数(株数)、被相続人の死亡時点での評価額を具体的に記載しましょう。
記載例は、以下の通りです。
- ・株式: 〇〇証券株式会社 〇〇株式会社 普通株式 1,000株 評価額 〇〇円
- ・投資信託: 〇〇証券株式会社 〇〇ファンド 10,000口 評価額 〇〇円
- ・国債: 種類 〇〇国債 額面 〇〇円 評価額 〇〇円
有価証券の評価は変動するため、死亡時点の正確な評価額を証券会社に確認してください。
不動産の記載例
不動産を相続財産目録に記載する際には、土地と建物に分けて、それぞれの所在地や地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを詳細に記載し、最後に固定資産税評価額を記入します。
記載例は、以下の通りです。
- ・土地: 所在地 〇〇市〇〇町〇丁目 地番 123番45 種類 宅地 面積 〇〇㎡ 固定資産評価額 〇〇円
- ・建物: 所在地 〇〇市〇〇町〇丁目 家屋番号 123番45 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階〇〇㎡ 2階〇〇㎡ 固定資産評価額 〇〇円
不動産の評価は複雑なため、固定資産税評価証明書や登記事項証明書などの公的資料に基づき、正確な情報を記載しましょう。
保険の記載例
保険を相続財産目録に記載する際には、保険の種類(生命保険、学資保険など)をはじめ、保険会社名や証券番号、契約者、被保険者、受取人、被相続人の死亡時点での解約返戻金相当額、または死亡保険金額を具体的に記載します。
記載例は、以下の通りです。
- ・生命保険: 〇〇生命保険株式会社 〇〇保険 証券番号 123456789 契約者 故〇〇〇〇 被保険者 故〇〇〇〇 受取人 〇〇 解約返戻金 〇〇円(または死亡保険金 〇〇円)
保険金は受取人固有の財産となる場合があるため、その点も考慮して記載しましょう。
負債の記載例
負債を相続財産目録に記載する際には、借入先の名称や借入の目的、契約年月日、残高など、具体的な情報を明確に記載します。
記載例は、以下の通りです。
- ・銀行ローン: 〇〇銀行 借入目的 自宅購入 契約日 20XX年XX月XX日 残高 〇〇円
- ・クレジットカード債務: 〇〇カード株式会社 利用目的 日常利用 残高 〇〇円
- ・未払金: 〇〇病院 未払医療費 〇〇円
負債は相続放棄や限定承認を検討するうえで欠かせない情報となるため、漏れなく正確に把握し、記載するようにしてください。
相続財産目録に関するよくある質問

ここでは、相続財産目録に関するよくある質問に回答します。
Q.相続財産目録は必ず作成しなければいけませんか?
A.相続財産目録の作成は、法律で義務付けられているわけではありません。
しかし、遺産分割協議を進める際や相続税の申告を行う際には、財産の全体像を把握するべく、実質的に作成が必須です。
また、相続放棄や限定承認の手続きを行う場合にも、財産目録の提出する必要があります。
Q.相続財産目録はどのような場面で役立ちますか?
A.相続財産目録は、相続手続きのさまざまな場面で役立ちます。
- ・遺産分割協議:相続人全員で公平な遺産分割を行うための基礎資料になる
- ・相続税の申告:相続財産の総額を正確に把握し、納税額を算出するために必要
- ・相続放棄・限定承認:マイナスの財産が多い場合に、検討する際の判断材料となる
- ・不動産の名義変更:不動産登記を行う際に、対象となる不動産の情報確認に活用できる
- ・預貯金の解約:金融機関での手続きに必要な情報を整理できる
財産目録を作成すれば、手続きがスムーズに進むほか、トラブルの回避につながるでしょう。
Q.相続財産目録の作成は弁護士に依頼できますか?
A.はい、相続財産目録の作成を弁護士に依頼することは可能です。
相続財産の調査から複雑な財産の評価、正確な目録の作成まで、一連の作業を代行してもらえます。
特に財産の種類が多岐にわたる、相続人同士の関係が複雑で公平な評価が難しい、借金などマイナスの財産が多い場合には、弁護士に依頼すると正確かつ円滑な手続きが期待できるでしょう。
まとめ
相続財産目録とは、被相続人のすべてのプラス・マイナス財産を一覧にまとめた書類です。
遺産分割協議や相続税申告、相続放棄・限定承認など、相続手続きのさまざまな場面で欠かせない役割を果たします。
相続財産目録は、まず故人の財産を隈なく調査し、それぞれの財産を特定するための資料を収集します。最後にそれらを整理して、作成する流れです。
なお、記載すべき主な項目には、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があり、両者を明確に区別して記載する必要があります。不動産については固定資産税評価額算出のポイントがあり、パソコンで作成した場合はすべてのページに署名捺印をしなければいけません。
相続財産目録は法律で義務付けられてはいませんが、遺産分割を円滑に進め、相続税申告を行ううえで実質的に必須です。遺産分割協議や相続税申告、相続放棄・限定承認、不動産、預貯金の手続きなどで役立つでしょう。
徳島県鳴門市の泉法律事務所では、相続財産目録の作成に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、ご依頼者様の状況を丁寧にヒアリングし、複雑な財産調査から正確な相続財産目録作成まで、きめ細やかにサポートいたします。
相続財産の全体像を明確にし、その後の遺産分割協議や相続税申告がスムーズに進むようお手伝いさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

