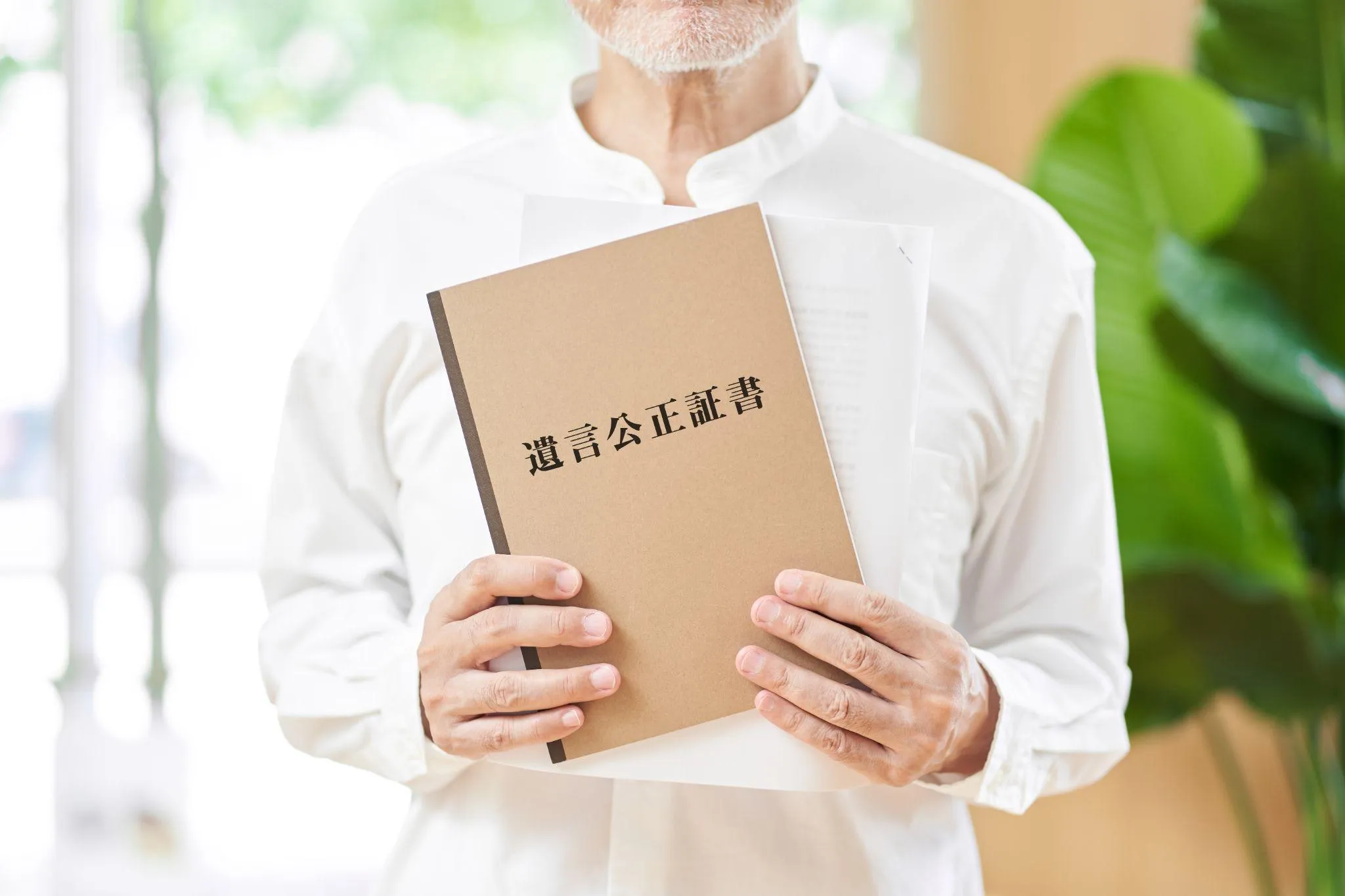
ご自身の死後、大切な家族が遺産分割で揉めたり、財産の行方について争ったりするのではないかと不安を覚える方もいるでしょう。
特に、遺言書を作成するにあたり、法的な有効性や効力に関する心配は尽きないものです。
遺言書は財産を誰にどのように遺すのか、その意思を明確にする手段です。しかし、種類によっては、形式不備で無効になったり、家庭裁判所の検認手続きが必要になったりと、相続人に負担をかける場合があります。
この記事では、公正証書遺言が持つ3つの効力と発生するタイミング、無効になる7つの要因について詳しく解説します。
公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記して作成します。なお、2人以上の証人の立ち会いも必要です。
また、公証人が法律の専門家として関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低い特徴があります。原本が公証役場に保管されるため、偽造や変造、紛失の心配が少ない点がメリットです。
相続発生後には、家庭裁判所での検認が不要なため、相続人の手続き負担を軽減できます。
公正証書遺言が持つ3つの効力

公正証書遺言は、他の形式の遺言書と比較して強力な効力を持ちます。
遺言者の意思を確実にし、相続発生後のトラブルを未然に防ぐうえで大きな役割を果たすでしょう。
公証人が関与することで得られる効力は、大きく分けると3つあります。
- ・遺言者の意思を実現できる
- ・形式不備によって無効になるリスクが低い
- ・公証役場で遺言者が120歳になるまで保管される
ここでは、公正証書遺言が持つ3つの効力をそれぞれ詳しく解説します。
遺言者の意思を実現できる
公正証書遺言は、遺言者の意思を確実にできる遺言書です。
公証人が遺言者の口述に基づいて作成するため、法的な解釈の曖昧さが少なく、内容が明確になります。これにより、相続人同士が遺言内容で争う可能性を大幅に減らせるでしょう。
また、遺言者が誰に何を遺したいかという具体的な意思が、法的に有効な形で文書化されるため、遺言執行がスムーズに進む可能性が高いです。
その結果、遺言者の願いが叶い、残された家族間の無用な争いを避けられます。
形式不備によって無効になるリスクが低い
公正証書遺言の効力は、形式不備によって無効になるリスクがきわめて低い点です。
自筆証書遺言の場合、日付の記載漏れや押印がないなどの形式不備で無効になるケースが少なくありません。しかし、公正証書遺言は公証人が法律に基づいて正確な手続きで作成するため、そのような心配が不要です。
また、法律の専門家である公証人が関与し、遺言書が民法に定められた要件をすべて満たしていることが保証されます。
これにより、相続発生後に遺言書が無効だと主張されるリスクを回避できます。
公証役場で遺言者が120歳になるまで保管される
公正証書遺言は、遺言者が亡くなるまで、または遺言者が120歳になるまで、公証役場で安全に保管されます。
これにより、遺言書を紛失したり、第三者によって偽造・変造されたりする心配がありません。
自筆証書遺言のように自宅で保管していて、相続人が発見できない、あるいは故意に隠されてしまうなどのリスクもないでしょう。
相続が発生した際には相続人が公証役場に問い合わせると、遺言書の存在を確認し、謄本の交付を受けられます。
公正証書遺言の効力が発生するタイミングと時効

公正証書遺言の効力が発生するタイミングは、遺言者の方が亡くなった時です。
遺言は遺言者が生存している間はいつでも撤回や内容の変更が可能であり、効力は発生しません。しかし、遺言者が亡くなると同時に、遺言書に記載された内容が法的な効力を持ちます。
したがって、遺言書の内容に従い、相続財産が承継される流れとなるでしょう。
また、公正証書遺言には消滅時効はありません。遺言者が亡くなった後であれば、何年経過しても遺言書としての効力は失われません。
ただし、相続財産の不動産登記(名義変更)は、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されたため、所有権の取得を知ってから3年以内に行う必要があります。
加えて、相続税の申告には期限が設けられており、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
遺言書そのものに時効はないものの、関連する法的手続きには期限があるため注意しましょう。
公正証書遺言の効力が無効になる6つの要因

公正証書遺言の効力は、特定の状況下では効力が無効になる可能性があります。
- ・遺言能力の欠如
- ・口授を欠いている
- ・証人や立会人の欠格事由に該当
- ・公序良俗に反する内容の記載
- ・詐欺・強迫・錯誤によって作成
- ・遺留分侵害
時間と費用をかけて作成した公正証書遺言が無効にならないよう、注意点を把握しておきましょう。
ここでは、公正証書遺言の効力が無効になる6つの要因をそれぞれ詳しく解説します。
遺言能力の欠如
公正証書遺言が無効となる要因に、遺言能力の欠如があります。
遺言能力とは遺言の内容を理解し、結果を判断できる精神的な能力です。
例えば、認知症が重度に進行している、精神的な疾患により判断能力が著しく低下している状態で遺言書を作成すると、無効となる可能性があります。
公証人は遺言者の遺言能力を確認しますが、後日、相続人から遺言時には遺言能力がなかったと争われるケースも珍しくありません。遺言能力が不十分だと判断されれば、法的な効力はなくなります。
口授を欠いている
公正証書遺言は遺言者が公証人に対し、遺言内容を口頭で伝える口授(こうじゅ)が必須です。
口授を欠いている場合、公正証書遺言は無効です。
例えば、遺言者が文字を書けず、事前に用意した文章を公証人に渡しただけで、口頭での説明を一切行わなかったようなケースがあったとしましょう。その場合、口授は認められず、遺言が無効となる可能性があります。
遺言者の意思が公証人に直接伝えられなければ、正式な手続きにはなりません。
証人や立会人の欠格事由に該当
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人または立会人の立ち会いが必要です。
証人や立会人が法律で定められた欠格事由に該当する人物であった場合、遺言は無効となります。欠格事由には推定相続人(遺言者の子や配偶者など)や、遺言によって財産を受け取る人、未成年者、公証人の配偶者や親族などが含まれます。
証人は遺言者が遺言内容を口授し、公証人が正確に筆記したことを確認する役割を担うため、適格性が厳しく定められているのが特徴です。
公序良俗に反する内容の記載
公正証書遺言の内容が、公序良俗に反すると無効です。
例えば、愛人に対して多額の財産を遺贈する代わりに、特定の行為を強制する内容や犯罪を助長するような内容などが該当します。
法律は社会の一般的な道徳観念や倫理に反する行為を許容しないため、遺言書であっても原則は適用されます。
つまり、遺言者の意思であっても、社会的に許容されない内容は法的な効力を持ちません。
詐欺・強迫・錯誤によって作成
遺言者が詐欺や強迫(脅し)、または錯誤(勘違い)によって遺言書を作成した場合、その公正証書遺言は無効となる可能性があります。
例えば、相続人から嘘を吹き込まれて不利な内容の遺言を作成させられたり、脅されて特定の人物に財産を遺贈するよう指示したりした場合などです。
また、遺言者が財産の内容や、相続人の認識に誤りがあった状態で作成した場合も、錯誤による無効を主張できる可能性があります。
遺言は遺言者の自由な意思に基づいて作成されるべきであり、外部からの不当な影響があれば効力は認められません。
遺留分侵害
公正証書遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害していると、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の相続割合です。
例えば、全財産を特定の相続人1人に遺贈する内容の遺言書を作成した場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。
この場合、侵害された相続人は、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できるため、遺言者の意図通りに相続財産が承継されない結果となるでしょう。
公正証書遺言の効力に関するよくある質問

公正証書遺言は確実性を持っているものの、効力や運用など実際に直面する状況ではさまざまな疑問が生じます。
ここでは、公正証書遺言の効力に関するよくある質問に回答します。
Q.公正証書遺言の内容に従わなければいけませんか?
A.原則として、公正証書遺言の内容には法的な拘束力があり、相続人はこれに従う必要があります。
しかし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。これは、相続人全員の意思が遺言者の意思に優先する、という考え方に基づいています。
ただし、遺言書に遺贈(遺言によって財産を贈与すること)の記載があり、受遺者(遺産を受け取る人)が相続人以外である場合、受遺者の同意も必要となるでしょう。
全員の合意が得られない場合は、公正証書遺言の内容通りに遺産分割が進みます。
Q.公正証書遺言の内容に納得できない場合は?
A.公正証書遺言の内容に納得できない場合でも、基本的には効力は有効です。
しかし、遺言書が無効となる7つの要因(遺言能力の欠如、口授の欠如、証人の欠格事由、公序良俗に反する内容に該当、詐欺・脅迫・錯誤、遺留分侵害など)に該当する可能性がある場合は、遺言無効確認の訴えを提起できます。
また、遺言書によってご自身の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求が可能です。
これは遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利であり、遺言書の内容を直接覆すものではありませんが、最低限の権利を確保できます。
Q.認知症の遺言者が作成した公正証書遺言にも効力はありますか?
A.認知症の遺言者が作成した公正証書遺言であっても、遺言時に遺言能力が認められれば、効力は有効です。
公証人は遺言を作成する時に、遺言者の意思能力を慎重に確認します。
しかし、認知症の進行度合いはさまざまであり、後日、相続人から遺言時には遺言能力がなかったと争われるケースも珍しくありません。
そのため、遺言能力の有無は、医師の診断書や当時の状況を示す客観的な証拠に基づいて判断されるでしょう。
不安がある場合は事前に専門家へ相談し、医師の診断や鑑定を受けるなど、遺言能力の証拠を残す対策をとるべきです。
まとめ
公正証書遺言とは公証役場で公証人が作成し、2名以上の証人の立ち会いのもと作成される、法的な有効性が高い遺言書です。
主な効力は遺言者の意思を確実に実現できる点、形式不備によって無効になるリスクが低い点、原本が公証役場で安全に保管される点が挙げられます。これにより、遺言者が希望する通りの財産承継が期待でき、将来の相続トラブルを大きく減らせるでしょう。
また、効力は遺言者が亡くなった時に発生し、遺言書自体に時効はありません。ただし、相続登記や相続税の申告には期限があるため、関連する手続きには注意が必要です。
なお、遺言能力の欠如、口授の欠如、証人や立会人の欠格事由への該当、公序良俗に反する内容の記載、詐欺・強迫・錯誤によって作成された場合、遺留分侵害などは公正証書遺言の効力が無効になる可能性があります。
これらに注意し、適正な手続きで作成することが、遺言書の有効性を保つために欠かせません。
ただし、原則として遺言内容に従う必要があるものの、相続人全員の合意があれば異なる分割も可能です。内容に納得できない場合は、無効確認の訴えや遺留分侵害額請求が検討できます。
徳島県鳴門市の泉法律事務所では、公正証書遺言の作成に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、ご依頼者様の状況や希望を丁寧にお伺いし、最適な遺言内容の検討から公証人との調整、証人の手配まで、きめ細やかにサポートいたします。
ご自身の意思を確実に未来に遺し、大切なご家族が争うことなく、円満な相続を実現するためのお手伝いをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

