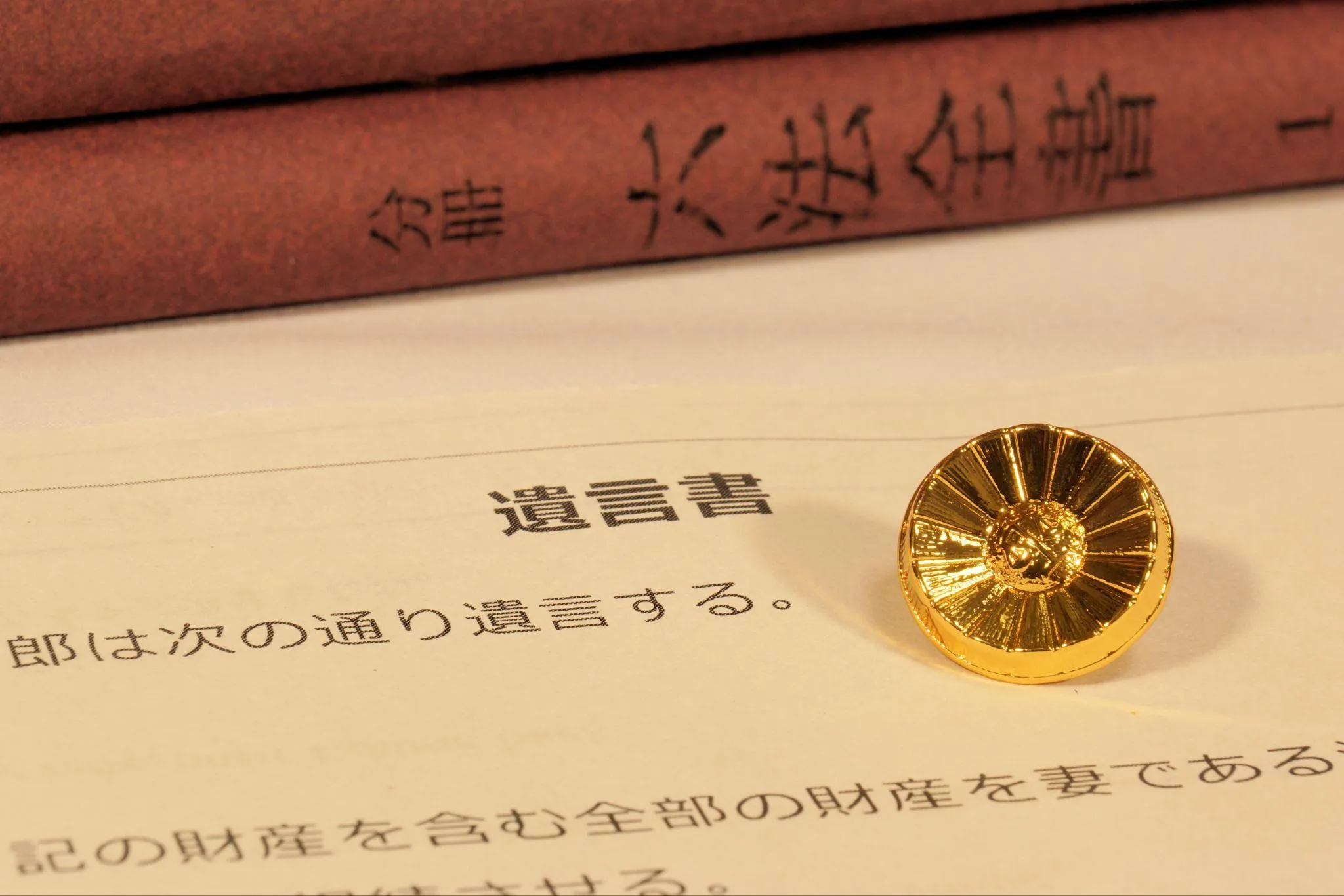
遺言書を作成すると、自身の意思を明確に伝えられるため、残された家族間の無用な争いを避けられる可能性が高まります。
しかし、遺言書の作成には法的な要件が多く、形式不備で無効になるリスクや、内容が不明瞭でかえってトラブルの原因になるのではないかと、懸念を抱いている方は多いはずです。
自力での作成も可能ですが、法律の専門知識が不足していると、思わぬ落とし穴にはまる場合があります。
この記事では、遺言書作成を弁護士に依頼する6つのメリット、依頼の流れや費用、選び方のポイントを詳しく解説します。
遺言書作成を弁護士に依頼する6つのメリット

遺言書作成を弁護士に依頼すると、意思を確実に未来に遺せるほか、相続トラブルを未然に防げる可能性があります。
主なメリットは、以下の通りです。
- ・形式不備による無効リスクが下がる
- ・有効な内容を書くサポートをしてくれる
- ・相続財産を調査してくれる
- ・遺言執行者としてもサポートしてくれる
- ・相続税の節税対策に関するアドバイスを受けられる
- ・万が一の相続トラブルにも対応してもらえる
ここでは、遺言書作成を弁護士に依頼する6つのメリットを詳しく解説します。
形式不備による無効リスクが下がる
遺言書作成を弁護士に依頼すると、形式不備による無効のリスクを大幅に下げられます。
遺言書には民法で定められた厳格な形式要件があるため、日付の記載漏れ、署名・押印の不備、証人の欠格事由への該当など、些細なミスでも無効となりやすいです。弁護士はこれらの要件を熟知しており、法的に有効な遺言書を作成するための適切なアドバイスとサポートを提供します。
これにより、せっかく作成した遺言書が、後になって無効だと主張される事態を避けられるでしょう。
有効な内容を書くサポートをしてくれる
弁護士は遺言書の内容が法的に有効であり、自身の意思を正確に反映したものになるようサポートしてくれます。
例えば、特定の財産を誰に遺すのか、遺留分を侵害しないように配慮するにはどうすべきかなど、具体的な財産状況や家族構成に応じた最適な内容を提案してくれるでしょう。
また、曖昧な表現を避け、将来的な解釈の齟齬が生じない文言で作成してくれます。
これにより、遺言書が願い通りに実行され、相続人間に争いが生じる原因を取り除けます。
相続財産を調査してくれる
弁護士は遺言書の作成に際して、相続財産の調査もサポートしてくれます
自身が把握していない預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、金融機関や役所への照会を通じて全容を明らかにしてくれるでしょう。
財産における全体像の把握は、遺言書に漏れなく財産を記載するために欠かせません。
また、隠れた財産や負債が発覚することで生じる相続トラブルを、未然に防げる可能性が高まります。
遺言執行者としてもサポートしてくれる
弁護士を遺言執行者に指定すると、相続発生後の遺言内容の実現を円滑に進められます。
遺言執行者は遺言書に記載された内容に従って、相続財産の名義変更や預貯金の解約、遺産の分配などを実行する役割を担うのが一般的です。
相続人の中から遺言執行者を選任すると、相続人に負担がかかるだけでなく、他の相続人から不公平だと見られる可能性があるでしょう。
このようなケースで弁護士が遺言執行者となれば、公平かつ迅速な手続きが期待できるほか、相続人間の無用なトラブルを回避できます。
相続税の節税対策に関するアドバイスを受けられる
弁護士は、相続税の節税対策に関するアドバイスも提供できます。
税理士のような具体的な税務申告を行うわけではありませんが、遺言書を作成する段階で、財産の種類や配分方法によって相続税額が変わる可能性について説明してくれるでしょう。
例えば、特定の財産を公益法人に寄付する、生前贈与を計画的に行うなど、遺言書の記載内容を工夫し、税負担を軽減できる可能性があります。
これにより、遺言者の意思を実現しつつ、相続人の負担を考慮した遺言書の作成が可能です。
万が一の相続トラブルにも対応してもらえる
弁護士に遺言書の作成を依頼すると、相続トラブルに発展した場合に対応してもらえます。
弁護士は依頼者の財産状況や家族関係を把握しているため、トラブルが発生した時には迅速かつ的確な対応が期待できるでしょう。
例えば、遺言書の解釈を巡る争いや遺留分侵害の請求など、法的な紛争に発展した場合でも、依頼実績のある弁護士がそのまま代理人として対応できます。
そのため、改めて弁護士を探す手間や時間を省けます。
遺言書作成の弁護士費用

遺言書作成を弁護士に依頼する際には、いくつかの費用が発生します。
- ・相談料
- ・遺言書の作成費用
- ・遺言書の保管費用
- ・手数料
- ・日当
これらは弁護士事務所や遺言書の種類、財産の規模などによって異なるため、注意が必要です。
ここでは、遺言書作成の弁護士費用について詳しく解説します。
相談料
弁護士に遺言書の作成について相談する際は、初回に相談料が発生する場合があります。
遺言書作成の依頼に進むかどうかに関わらず発生する費用です。
法律事務所の多くは、30分または1時間あたり5,000円~10,000円ほどの相談料を設定しています。
しかし、最近では初回相談を無料で提供している事務所も増えているため、比較検討する際は費用が必要かどうかを考慮するとよいでしょう。
遺言書の作成費用
遺言書の作成費用は、弁護士に支払う報酬です。
遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)、財産の規模や内容、相続人の人数、遺言書の内容の複雑さによって大きく異なります。
一般的な目安は、自筆証書遺言の作成サポートが数万円から、公正証書遺言の作成サポートで10万円~30万円ほどかかるでしょう。
これらの費用には弁護士が遺言書の内容を検討し、文案を作成する労力や法的な助言に対する報酬が含まれます。
遺言書の保管費用
遺言書を弁護士事務所で保管してもらうと、保管費用が発生する場合があります。
相場は年間で数千円~1万円ほどが一般的ですが、事務所によって異なります。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されますが、写しを弁護士に預けると相続発生時に速やかに対応してもらえる点がメリットです。
自筆証書遺言の場合は、紛失や改ざんのリスクを避けるためにも、弁護士による保管が有効といえるでしょう。
手数料
遺言書の作成に関連して、弁護士が各種手続きを代行する場合に手数料が発生するケースがあります。
例えば、公正証書遺言を作成する際には、公証役場に支払う手数料が必要です。また、財産調査のために役所から書類を取得したり、金融機関へ照会したりする際に発生する実費なども、手数料として計上される場合があります。
これらの手数料は弁護士の報酬とは別に、実費として依頼者が負担する費用となるでしょう。
日当
弁護士が遠方への出張が必要となる場合、裁判所、公証役場などへ出向く際に、日当が発生する場合があります。
日当は、弁護士が事務所を離れて活動する時間に対する費用です。半日あたり数万円、1日あたり数万円〜10万円ほどがかかる傾向にあります。
例えば、公正証書遺言の作成時に公証役場へ同行してもらう、病気などで弁護士が遺言者の自宅を訪問する場合などに適用されるでしょう。
依頼する前に、どのような場合に日当が発生するのか確認しておいてください。
弁護士に依頼した遺言書作成の流れ

弁護士に遺言書作成を依頼する際、どのような手順で進んでいくのかを事前に把握しておくべきです。
一般的には、最初の相談から遺言書の完成まで、以下のようなステップを踏んでいきます。
- 初回相談・契約
- 財産の調査および必要書類の収集
- 遺言書の文案作成
- 遺言書の内容確認と修正および作成
- 公証役場での手続き
ここでは、弁護士に依頼した遺言書作成の流れを詳しく解説します。
初回相談・契約
まずは弁護士事務所に連絡を取り、初回相談を行います。
遺言書作成を希望する理由をはじめ、財産の状況、相続人に関する情報、希望など、具体的な状況を弁護士に伝えましょう。
弁護士は情報に基づいて、どのような遺言書が必要か、費用はどのくらいかなどを説明してくれます。
相談後に弁護士への依頼を決めたら、委任契約が締結され、正式依頼となります。
財産の調査および必要書類の収集
契約が締結したあとは、弁護士が遺言書作成に必要な財産の調査と、関連書類の収集をサポートします。
所有する財産の種類や規模を正確に把握するため、預貯金や不動産、有価証券などの具体的な情報を確認するでしょう。
また、戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書など、遺言書作成や公証役場での手続きに必要な書類の収集も支援してくれます。
遺言書の文案作成
財産調査と書類収集が完了したら、弁護士は依頼者の希望と法的な要件に基づき、遺言書の文案を作成します。
遺留分などの相続に関する民法の規定を考慮し、相続トラブルを避けるための内容を盛り込んでくれるでしょう。また、依頼者の意思が曖昧にならないよう、明確で具体的な表現を用いて文案を作成します。
ただし、この文案はあくまで仮のものであり、次の段階での確認と修正を経て、最終的な形に近づけていくのが一般的です。
遺言書の内容確認と修正および作成
遺言書の文案が完成したら、依頼者が確認するステップに入ります。
内容に意思が正確に反映されているか、不明瞭な点や修正したい点がないかなどを弁護士に伝え、必要に応じて調整を加えてください。
このやり取りを何度か繰り返し、納得できる文案が完成したら、最終的な遺言書の作成に進みます。
公正証書遺言の場合はこの段階で公証役場との調整も進められ、作成日などが決定されるでしょう。
公証役場での手続き
公正証書遺言を作成する場合は、最終的に公証役場での手続きが必要です。
弁護士は依頼者の公証役場への同行を手配し、当日も立ち会ってくれます。公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを筆記し、依頼者と証人が内容を確認して署名・押印を行う流れです。
また、自筆証書遺言の場合も保管制度の利用をサポートするなど、遺言書の確実な保管に向けたアドバイスを提供してくれるでしょう。
遺言書作成を依頼する弁護士選びのポイント

遺言書作成を弁護士に依頼する際は、以下のポイントを押さえて選びましょう。
- ・無料相談を活用して複数の弁護士を比較
- ・相談しやすい立地にあるか
- ・相談時間が自分のライフスタイルに合っているか
- ・税理士との連携があるか
ここでは、遺言書作成を依頼する弁護士選びのポイントを詳しく解説します。
無料相談を活用して複数の弁護士を比較
遺言書作成を依頼する弁護士を選ぶ際は、複数の法律事務所の無料相談を活用し、比較検討するべきです。
無料相談では弁護士の話し方や説明の分かりやすさ、疑問に対する回答の的確さ、相性などを確認できます。
複数の弁護士と話せば、それぞれの専門性や対応の違いを比較できるため、もっとも信頼できると感じる弁護士を見つけられるでしょう。
相談しやすい立地にあるか
弁護士事務所の立地が相談しやすい場所にあるかも、弁護士選びでは欠かせないポイントです。
特に、遺言書作成の過程では、弁護士との面談が何度か必要になる可能性があります。自宅や職場からのアクセスが良く、交通の便が良い場所にある事務所であれば、移動の負担を減らせるでしょう。
また、公証役場へのアクセスも考慮に入れると、手続きがよりスムーズに進むはずです。
相談時間が自分のライフスタイルに合っているか
弁護士事務所が提供する相談時間が、ライフスタイルやスケジュールに合っているかも確認するべきです。
例えば、平日の日中に時間が取りにくいなら、夜間や土日の相談に対応している事務所を選ぶとよいでしょう。また、オンラインでの相談に対応しているかどうかも、遠方に住んでいたり移動が困難だったりする場合に欠かせないポイントです。
柔軟な対応をしてくれる弁護士を選べば、無理なく遺言書の作成を進められます。
税理士との連携があるか
遺言書の作成を依頼する弁護士が、税理士と連携しているかどうかも、確認すべきポイントです。
相続財産には相続税がかかる場合があるため、遺言書の内容によっては税額が大きく変動する場合があります。
税理士と連携している弁護士なら、遺言書の作成と並行して相続税に関するアドバイスを受けられるほか、税務対策まで含めたサポートを期待できるでしょう。
これにより、法的な有効性と税務的な効率性の両面から最適な遺言書を作成できます。
まとめ
遺言書作成を弁護士に依頼すると、形式不備による無効リスクの低減、有効な内容作成のサポート、相続財産調査など、多くのメリットを得られます。
法律の専門家である弁護士の知識と経験を活用すれば、あなたの意思を確実に反映できるほか、相続トラブルを未然に防げるでしょう。
また、相性の良い弁護士を選ぶと、質の高いサポートを受けられます。
徳島県鳴門市の泉法律事務所では、遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、ご依頼者様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、法的に有効かつご自身の意思を最大限に尊重した遺言書作成をサポートいたします。
相続トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族が争うことなく円満な相続を実現するためのお手伝いをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

